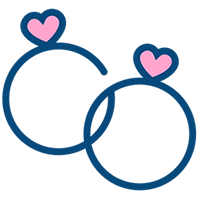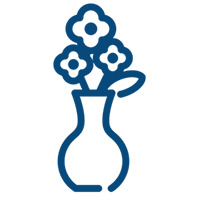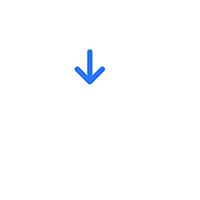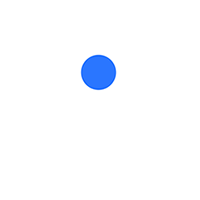法人市民税Q&A
Q1.法人市民税の納税義務者にはどのような種類がありますか。
A.市内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人や、収益事業を行う人格のない社団や財団で、法人とみなされるもので、主に次のようなものがあります。
- 公共法人…独立行政法人など
- 公益法人…社会福祉法人、社団法人、認可地縁団体、NPO法人、公益財団法人など
- 協同組合…農業協同組合、信用金庫など
- 人格のない社団…PTA、同窓会、学会、地縁団体、管理組合など
- 普通法人…株式会社、有限会社、医療法人など1から4までの区分に該当しないもの
Q2.公益社団法人、公益財団法人、地方自治法に規定する認可地縁団体、NPO法人は納税義務がありますか。
A.法人税法上の公益法人であっても、法人税法で定める収益事業を行う場合は、均等割と法人税割の申告納付義務があります。収益事業の定義は、法人税法で細かく定められていますので、その判断は管轄の税務署等にご相談ください。
収益事業を行わない公益社団法人、公益財団法人、認可地縁団体、NPO法人については、地方税法上、均等割の申告納付義務がありますが、須賀川市の場合、市税条例で減免の対象としています。減免を受けようとする場合、納期限(通常は4月末)の7日前までに、市に対し減免の申請が必要です。
Q3.社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合は納税義務がありますか。
A.地方税法第296条第1項第2号により、法人税法で定める収益事業を行えば、均等割及び法人税割の申告納付義務があります。収益事業を行わない場合は、均等割及び法人税割ともに納税義務はありません。ただし、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします。(地方税法施行令第7条の4)
Q4.赤字でも法人市民税はかかりますか。
A.赤字でも法人市民税はかかります。赤字の場合、法人税割は課税されませんが均等割は対象になりますので申告と納付が必要です。
Q5.法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのでしょうか。
A.均等割は市内に事務所等を有する法人と市が行う行政サービスとの応益関係に着目して、そのために要する市の経費の一部を求めるものです。このため、国税である法人税には均等割はありません。法人市民税の場合は9段階に分かれていますが、資本金等の額や従業者数が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。また、法人市民税の均等割は法人県民税と違い5万円から300万円までとなります。
Q6.収益事業とは何ですか。
A.法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業をさし、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。社会通念上の大部分の営業行為が含まれています。収益事業にあたるかどうかについては、管轄の税務署にお問い合わせください。
なお、具体的に収益事業になるものは次の34事業です。
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他の飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保健業
- 技芸教授業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権の提供等を行う事業
- 労働者派遣業
Q7.法人市民税における「事務所等」の要件について教えてください。
A.事務所等の要件として、人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件があります。
人的設備
- 人的設備とは、正規従業員だけでなく、法人の役員、清算法人における清算人、アルバイト、パートタイマーなども含みます。
- 人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮および監督に服する場合は人的設備となります。
- 規約上、代表者または管理人の定めがあるものについては、特に事務員等がいなくても人的設備があるとみなします。
物的設備
- 事務所等は、それが自己の所有であるか否かは問いません。
- 物的設備とは、事業に必要な土地、建物、機械設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。
- 規約上、特に定めがなく、代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも、そこで継続して事業が行われていると認められるかぎり、物的設備として認められます。
事業の継続性
- 事務所等において行われる事業は、個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等とします。
- 事業の継続性には、事業年度の全期間にわたり、連続して行われる場合のほか、定期的又は不定期的に、相当日数、継続して行われる場合を含みます。また、そこで事業が行われた結果、収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。
- 原則として、2、3か月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所、仮小屋などは事務所等に該当しません。
Q8.会社の寮が須賀川市にあるのですが法人市民税はかかりますか。
A.「地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う(地方税法294条第1項、24条第1項4号)」とされており、均等割のみがかかります。寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。
Q9.設立登記上、須賀川市内の社長宅を本店としましたが実際はB市で活動を行っています。須賀川市で課税されますか。
A.そこで継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとは言いがたいので均等割、法人税割ともに須賀川市では課税されませんが、事業活動がどこで行われているかを把握する必要があることから、法人設立届を須賀川市に提出し、須賀川市では事業を行っていない旨を申出ください。なお、法人設立届はB市にも提出が必要です。
Q10.公共法人で均等割のみの申告をする場合の税率と申告期限を教えてください。
A.均等割の税率は地方税法第312条で規定されており、年額5万円です。また申告期限は地方税法第321条の8第19項の規定により毎年4月30日です。また、年度中途で解散した場合も4月30日の期限に変わりありません。ただし、4月30日が土日に該当する場合は、翌月曜日になります。
Q11.中間申告と予定申告の違いは何ですか。
A.中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の二種類があり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを予定申告と呼んでいます。
Q12.均等割の従業者数について教えてください。
A.均等割の従業者数とは、その法人から俸給・給料・賃金・手当・賞与、そのほかこれらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。次の点において法人税割と異なります。
- 寮等の従業者数を含む。
- 従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない
- アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。
なお、棒給、給料もしくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員は、均等割の従業者数に含められます。
Q13.更正とは何ですか。
A.法人市民税では申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が確定します。しかし、申告の内容が課税庁で調査した結果と異なる場合、課税の公平を図るため、その内容を変更することが必要となります。これが更正です。税額を増加させるものを増額更正、減少させるものを減額更正といいます。
Q14.更正の請求と修正申告の違いを教えてください。
A.更正の請求とは、納税義務者が申告した税額が過大であることを知った場合に、納税義務者から課税庁の減額更正を求める行為のことです。修正申告とは税額を増加させる場合に認められるのに対し、更正の請求は税額を減少させる場合に認められます。ただし、修正申告と違い、更正の請求の場合は税額を確定させる効力はありません。
Q15.更正の請求には期間制限はありますか。
A.更正の請求ができる期間は法定納期限から5年以内です。ただし、次の場合は期限経過後も可能です。
- その申告、更正に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の基礎と異なることが確定したとき:その確定した日の翌日から起算して2か月以内。
- 法人住民税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由があるとき:当該理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内。
やむを得ない理由とは、地方税法施行令第6条の20第2項に定められています。
また、法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正の通知があった時は、その通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。ちなみに、課税庁が行う法人市民税の更正の期間制限は、法定納期限の翌日から5年です(地方税法17条の5第1項)。更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1か月後となります(地方税法321の12第1項、56条第1項)。この場合の「通知日」については、通知の初日を不算入とする規定がはたらくので、例えば、通知の日が5月15日の場合、納期限は6月16日(この日が休日に該当しないとき)となります(地方税法20条の5、民法140条)。
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。