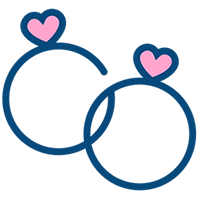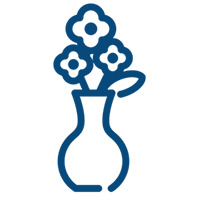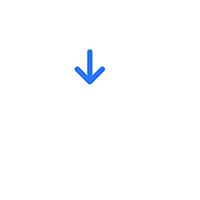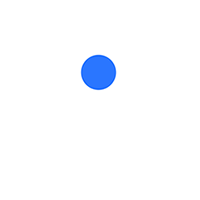令和5年度の取組
令和5年度の取組
<第10回会議>(令和5年6月29日開催)

令和5年度はじめての会議である第10回会議は、令和4年度の活動の振り返り、未来ビジョンの改定(案)、令和5年度の活動予定の3点について話し合いました。
令和5年度は、各種取組に「福祉」や「DX」、「GX」 などについても積極的に取り入れていきたいと考えており、エリプラ会議は令和4年度同様に4回の開催を予定しています。
また、DX関連事業として「官民連携まちなか再生推進事業」の補助メニュー「地域交流創造支援施設整備」を活用して“まちづくりDX交流拠点”の整備を行うこととしており、完成後は様々な大学のサテライト拠点などとしても活用していきたいと考えているとのことでした。
さらに、中高生を対象に地域の課題を解決するまちづくりDX人材育成プロジェクト「須賀川ワガママLab」を令和5年6月24日から開催しており、地域で暮らす人たちが普段の生活の中で諦めていることや我慢していることを“ワガママ”として可視化し、地域の人たちと連携しながらデジタルを活用して、地域課題を解決するアプリの開発に挑戦していているところです。

~須賀川ワガママLab~<第1回ワークショップ>(令和5年6月24日開催)

身近な誰かを想い、その人の「ワガママ」を叶えるアプリの開発へのチャレンジが、中高生8名の参加により始まりました。
第1回ワークショップでは、世界のスマートフォン流通数やアプリ開発の実例などについて学んだあと、実際にアプリ開発を行いました。
マサチューセッツ工科大学が提供するMIT App Inventorというプログラムを使用し、ボタンを押すと挨拶をするアプリや、須賀川市に訪れた観光客向けのアプリをつくりました。参加者の皆さんはアプリ作成に熱中していて、「うまくできない」「もっとこうしたらいいんじゃないか」と試行錯誤を繰り返していましたが、とても楽しんでいる様子でした。
~須賀川ワガママLab~<第2回ワークショップ>(令和5年7月19日開催)

第2回ワークショップは、はじめに須賀川市の各種データ(人口や職種分類など)を基にした須賀川市の現状の説明を受け、須賀川市はどういった課題を抱えているのかを知ることから始まりました。そのデータを踏まえ、須賀川市で暮らす誰のどんな課題を解決したいか考え、発表してもらいました。
「障害者の課題」「子どもを増やす」「過疎地域に住む人の買い物の不便さ」「保育園の赤ちゃん」「若者が須賀川市を離れるのを抑える」「1人で住んでるお年寄りの人」
など、これまで経験してきたことや生活環境、興味のあることは人によって異なるため、様々な視点から意見が出てきました。
次に、アプリの設計書となる構想シートを個人で書いた後、2人から3人が1つのチームとなって、持ち寄った構想シートをもとにアプリをつくり、発表してもらいました。つくられたアプリは次のとおりです。
「高齢者のために病院の情報を入れたアプリ」
「若い人たちが須賀川市を離れることを解決するアプリ」
「園児のバス置き去りを防止するためのアプリ」
今回はニュースなどで知った情報などから考え付いた課題を解決するためのアプリをつくりました。中高生でもしっかりと社会の問題、地域の課題を捉えることができていて、見守る大人たちが感心していました。
~須賀川ワガママLab~<フィールドワーク>(令和5年8月27日開催)

前半では、須賀川でも活動している学生団体ARCHI NEST(アーキネスト)の鈴木景大さんにインタビューしました。鈴木さんは日本大学工学部3年生でありながら増え続ける空き家を何とかしたいとの考えから、空き家のリノベーションを行う活動をしています。実際に活動している方からお話を聞くことで、より"地域の課題”の発見が身近に感じるようになりました。
次に、須賀川市で暮らすたったひとりのワガママを叶えるアプリをつくるために、須賀川市民のペルソナ(何か困っていることがある人のイメージ像)をつくりました。最初は難しく感じて手が止まってしまう場面もありましたが、実際に自分や家族をイメージして考えると、具体的なペルソナが思い浮かぶようになりました。
普段何気なく接している誰かにスポットを当てて、相手の立場になってその人のことを真摯に考える作業はいろいろな「気づき」を与えてくれました。みんなで出したペルソナから1つを選んでアプリにしていきました。まずはペルソナのイメージをより具体的にして、困っていること、解決したいことを考え、そのうえでスマートフォンアプリで解決できることは何かを考えました。
今回はアイコンも自分で決めてアプリ化しました。自分たちが一生懸命考えてつくったアプリがスマートフォンに表示されると、とても嬉しそうな様子でした。
今回作ったアプリは次のとおりです。
「ゲリラ豪雨が怖くて洗濯物を干せない人に向けて、どのくらいで雨が降ってくるのかが分かるように、須賀川市の天気予報が表示されるアプリ」
「LINEとショートメールを間違える高齢者に向けて、"連絡する”と書いてあるボタンを押すとLINEが立ち上がるアプリ」
これからはチームに分かれて、本格的にアプリをつくっていきます。
<第11回会議>(令和5年9月29日開催)

第11回会議は、未来ビジョン「みちしるべ」の3つのコンセプト「-Social-人と社会」「-Place-人と場」「-Environment-人と環境」に数名ずつ分かれて、未来ビジョンの実現に向けて今後どんな活動を展開していけばよいかを話し合いました。
「広いコミュニティ」をつくり、より「深いコミュニティ」にしていければ持続可能な活動になるのではないか、日替わりテーマ別コミュニティスペースがあればいいな、など、たくさんの意見があがりました。
こういった意見を参考に、これからのエリプラの活動に生かしていきたいと思います。
須賀川みらいラボオープンセレモニー&Wagamama Awards 同時開催(令和5年10月22日)
須賀川みらいラボオープニングセレモニー

令和5年度の官民連携まちなか再生推進事業「地域交流創造支援施設整備」の補助メニューを活用して整備した、"須賀川みらいラボ”のオープニングセレモニーを令和5年10月22日に行いました。
「須賀みらいラボ」は、須賀川市本町地内にあるNTT東日本が所有する施設の一角が空きスペースになっており、有効活用するためにリノベーションしたもので、地域内外の多様な人材の交流とDXによる地域課題の解決やデジタルを活用した地域の価値創造等を推進するための地域交流創造拠点です。地域内外の方々がリアル・オンラインどちらでも交流しやすいミーティング環境が整っており、柔軟なレイアウトが可能なコンベンションルーム、コワーキングスペースとなっています。
また。大規模災害時は情報発信拠点や簡易避難所として地域の皆さまへの施設開放も行うこととしています。
Wagamama Awards

オープニングセレモニー後は、約4か月間にわたり活動してきた須賀川ワガママLabの発表会「Wagamama Awards」を開催しました。

~挑戦することが不安な高校生の背中を押したい~
1チーム目は高校3年生、2年生のチームです。「誰のどんな課題を解決したいか」を話し合っていると、みんな共通した経験があることに気がつきました。
それは、なにか挑戦したいことがあっても1人だと一歩踏み出すのが不安で、あきらめたことがあるという体験でした。
実際にこのチームには、須賀川ワガママLabに参加することが1人だと心細かったので友達を誘ってきたというメンバーもいました。
挑戦したいという想いを持った高校生があきらめることがないように、挑戦しようとする高校生の背中を押せるアプリをつくることにしました。
アプリ内では、自分の目標を投稿することができて、さらに他の人の目標も見ることもできます。自分が掲げた目標と近い目標を持った仲間とLINEのオープンチャットのグループでつながれるようにしました。
また、須賀川市のバイトやボランティア情報も掲載して、挑戦できる機会も見つけられるようにしています。
何かやりたい、挑戦したいという高校生が仲間や行動できる機会を見つけ、自分がやりたいことをやれる人が増えるようになればという想いを込めています。

~おじいちゃんが友達をつくって楽しく暮らしてほしい~
次は中学生と高校生の混合チームです。身近な家族の困りごとを解決したいと考えた結果、みんな共通して感じていたのが、自分のおじいちゃんやおばあちゃんが人と関わる機会が少ないということでした。
高齢者の孤独は、日本全国で起きている地域課題のひとつです。調べていくと、須賀川市では高齢者向けのイベントはたくさんやっていることがわかりました。ではなぜ、自分たちのおじいちゃんやおばあちゃんはそこにいかないのでしょうか。
実際に本人への取材をしてみたところ、理由はそれぞれ違うことに気がつきました。最初はみんなで1つのアプリをつくろうとしていたのですが、自分のおじいちゃん、またはおばあちゃん専用のアプリをつくることにしました。

発表は、WEB会議システムを併用し、ワガママLabプログラム開発に携わる、マサチューセッツ工科大学認定・教育モバイルマスタートレーナーの石原先生にも見ていただき、コメントをいただきました。
「全ての発表が、みなさんの身近な体験を出発点としながら全国で起きている課題にアプローチしているものになりましたね。身近な人のためにつくったからこそ細かな点まで認識できていましたし、さらに「こんなふうに暮らしてほしい」という個人的な願望も入ってこだわったものになったのだと思います。統計から定量的に地域の動向もおさえている点も素晴らしかったです。世界に向けて発信するべき活動になったと思います。」<石原先生コメント>

参加してくれた学生の皆さんからも感想をいただきました。
「最後の1週間は発表に間に合うか心配でした。おばあちゃんのことを真剣に考えて、インタビューもしてつくれたので、楽しかったです。今回つくったアプリをおばあちゃんに使ってほしいです。」
「オンラインで作業したときは、zoomに入るところも難しくて大変でしたが、完成までできて良かったです。参加して良かったです。」
「たくさんの人が協力してくれたなと感じます。この班のメンバーで一緒につくれて良かったです。つくったアプリは実際に使ってもらえたらいいなと思います。この4か月間の経験をこれからに活かしていきたいです。」

アワード当日は、季節柄、体調を崩されたり試験日程などに重なってしまったりしたため、少人数での発表となりましたが、非常に濃い内容で充実したアワードを開催することができました。
参加してくれた学生の皆さん、本当に4か月間お疲れさまでした。
<第12回会議>(令和5年12月13日開催)

第12回会議は、令和6年度以降実施する取組について考えるため、東北電力フロンティア様や一般財団法人民間都市開発推進機構様の支援制度について情報提供いただいた後、未来ビジョン「みちしるべ」の3つのコンセプトで班に分かれて、テーマごとに実現可能な取り組みがないか話し合いました。
まちなか運動会やeスポーツ、防災キャンプや須賀川名産のキュウリを使ったイベントなど、様々なアイデアがたくさん出てきました。令和6年度以降の活動に向けて、エリプラメンバー全員がそれぞれの仕事(強み)を生かし、さらに自分ゴトとして進めていけるよう検討していきます。
<第13回会議>(令和6年2月28日開催)

第13回会議では、令和5年度の活動状況について報告された後、NTT東日本様、日本電気株式会社様より事業提案がありました。
NTT東日本様からは、前回の第12 回須賀川南部地区エリアプラットフォーム会議にて「e スポーツ」というご意見がでたため、NTT 東日本で実施しているe スポーツを活用した取組をご紹介いただきました。他地区の事例を紹介しつつ、須賀川南部地区での事業内容やスケジュールなどをご提案いただきました。
日本電気株式会社様からは、須賀川市の魅力や課題を明確にし、地域活性化の成功パターンと失敗パターンをご説明いただきました。また、日本電気株式会社で実施している集客情報分析「Field Analyst」をご紹介いただき、須賀川南部地区での活用方法についてご提案いただきました。
令和6年度は、よりアクションを推進していくため、部会に分かれて会議を行っていく予定です。
このページに関するお問い合わせ
建設部 都市計画課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
都市計画係 電話番号:0248-88-9154 ファクス番号:0248-73-4205
都市整備係 電話番号:0248-88-9155 ファクス番号:0248-73-4205
公園緑地係 電話番号:0248-88-9156 ファクス番号:0248-73-4205
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。