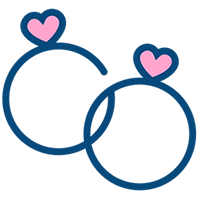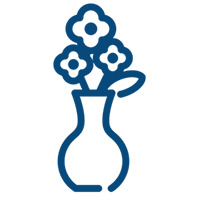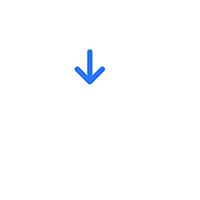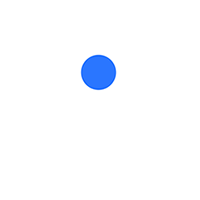【一般の部】すかがわ俳句検定2025(解答)
「すかがわ俳句検定2025 一般の部」の募集期間が終了しましたので、以下のとおり解答を公開します。
なお、全問正解した方には「すかがわ俳句検定2025合格証(一般の部)」を授与し、さらに、全問正解者の中から抽選で10名に景品を贈呈します。(合格証及び景品は9月中旬ごろ発送予定)
この度は、「すかがわ俳句検定2025 一般の部」にご参加いただき誠にありがとうございました。
問1 冬の季語は?(角川歳時記参照)
狸
「松茸」と「流星」は秋の季語です。
問2 夏の季語でないものは?(角川歳時記参照)
レモン
「レモン」は秋の季語です。
問3 「俳句」という呼び名は実は明治時代からと言われていますが、その前の呼び名は?
俳諧
「俳句」は、明治時代以前は「俳諧」と呼ばれていました。
問4 「あかまつ」は4音、では「ちょうちょ」は何音?
3音
「ちょ」「う」「ちょ」となるので3音です。小さい「ょ」などの拗音(ようおん)は、前の文字と合わせて1音と数えます。
問5 春の季語「桜」を表す言葉でないものは?
花野
「花筏」と「花朧」は桜を表す言葉です。「花野」は「秋の草花が咲き乱れる野原」を表す秋の季語です。
問6 一つの句に2つ以上の季語が入ることを何という?
季重なり
強く言い切る働きをする語(や・かな・けり 等)を「切れ字」といい、一つの語が二つの切れ目をまたいで使われることを「句またがり」といいます。
問7 「おくのほそ道」の書き出しである「月日は百代の過客にして」の「過客」の意味は?
旅人
「過客」は旅人を表す言葉です。
問8 国指定の名勝である「おくのほそ道の風景地」には、何カ所が指定されている?
26カ所
「おくのほそ道の風景地」には、令和7年8月現在、26カ所が登録されています。
問9 芭蕉が「おくのほそ道」の旅で訪れた日本三景の一カ所はどこ?
松島
芭蕉は「おくのほそ道」の旅で、日本三景の一カ所である「松島」を訪れました。
問10 芭蕉が「おくのほそ道」の旅で10日以上滞在した場所はどこ?
栃木県黒羽
芭蕉は、栃木県黒羽に14日間滞在しました。なお、岩手県平泉には数時間、福島県須賀川市には8日間滞在しました。
問11 「おくのほそ道」の旅のゴールは、岐阜県のどこか?
大垣市
芭蕉は「おくのほそ道」の旅を岐阜県大垣市でむすびました。
問12 芭蕉は何人で「おくのほそ道」の旅をしたか?
2人
芭蕉は、弟子である「河合曽良」と一緒に「おくのほそ道」の旅をしました。
問13 芭蕉が生まれた場所は?
伊賀市
芭蕉は現在の三重県伊賀市に生まれました。
問14 芭蕉が「おくのほそ道」の旅で移動した距離は?
約2,400km
芭蕉は「おくのほそ道」の旅で、約2,400kmの距離を移動しました。
問15 次の句は芭蕉が須賀川市で詠んだ句です。この句にある「栗の花」はいつの季語?「世の人の見つけぬ花や軒の栗」
夏
「栗の花」は夏の季語です。
問16 芭蕉が「おくのほそ道」で福島県に入ったのは今の暦でいつ?
6月7日(旧暦4月20日)
芭蕉が「おくのほそ道」の旅で福島県に入ったのは、6月7日(旧暦4月20日)です。
問17 「風流の初やおくの田植うた」の季語はどれでしょう?
田植うた
「風流の初やおくの田植うた」の季語は、「田植うた」(夏の季語)です。
問18 須賀川市滞在3日目に、可伸の庵にて芭蕉にそばきりを振舞ったのは誰か?
吉田祐碩(よしだゆうせき)
須賀川の俳人である「吉田祐碩」が、可伸の庵にて芭蕉にそばきりを振舞いました。
問19 芭蕉が訪れた時の須賀川はどんな町?
宿場町
当時の須賀川は、奥州街道屈指の宿場町として栄え、町人文化も花開く活気に満ちた町でした。
問20 芭蕉が須賀川に滞在した理由は?
須賀川に住む友人に会っていたから
芭蕉は、心を通わせる友人・等躬に会い、ともに句作の時間を過ごすために須賀川に滞在しました。
問21 須賀川の女流俳人である市原多代女の生まれた家の家業は?
造酒屋
市原多代女は造酒屋の家庭に生まれ、生涯で4,000句余りの俳句を詠みました。
問22 次の句を詠んだ俳人は?「あの辺はつく羽山哉炭けふり」
相楽等躬
相楽等躬は問屋業を営む豪商で、須賀川宿の駅長を勤める傍ら須賀川俳壇の中心的な人物でした。
問23 次の句を詠んだ俳人は?「どの道をゆきても雪のさびしさよ」
道山草太郎
祖父の壮山の俳系を継ぎ、詩人的資質と求道精神とが一体となった独自の俳境を拓き、須賀川俳壇の興隆に尽力した人物です。
問24 須賀川俳諧の祖といわれる相楽等躬の句碑がある場所は?
長松院(ちょうしょういん)
須賀川市諏訪町にある「長松院」に相楽等躬の「あの辺はつく羽山哉炭けふり」の句碑があります。なお、「長松院」には相楽等躬のお墓もあります。
問25 相楽等躬のあとを継いだ須賀川の俳人は?
藤井晋流
相楽等躬の後継者として蕉風俳諧の継承に努めた人物です。
問26 須賀川の風景、旅情の句を投稿していただくため、市内複数カ所に設置されているものは?
俳句ポスト
市民や須賀川に訪れた人が気軽に俳句を投稿できるよう、市内複数カ所に「俳句ポスト」が設置されています。
問27 2024年7月より「風流のはじめ館」で配布されているマンホールカードにデザインされている句は?
風流の初やおくの田植うた
「風流のはじめ館」で配布されているマンホールカードには、「風流の初やおくの田植うた」の句がデザインされています。
問28 牡丹焚火は、平成13年に環境省の「◯◯◯風景100選」に選ばれました。◯に入る文字は?
かおり
「牡丹焚火」は、平成13年に環境省の「かおり風景100選」に選ばれました。
問29 牡丹焚火の始まりは何時代か?
大正
牡丹焚火は大正時代に、園主柳沼源太郎が古木を供養するためにひっそりと焚いていたことが始まりです。
問30 次の句を詠んだ俳人は?「北斗祭るかむなき心牡丹焚く」
柳沼破籠子(やぎぬまはろうし)
父祖伝来の牡丹栽培に専念する一方、俳人としても優れた才能を発揮し、数々の牡丹の名句を残した人物です。
このページに関するお問い合わせ
文化交流部 文化振興課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
文化振興係 電話番号:0248-88-9172 ファクス番号:0248-94-4563
文化財係 電話番号:0248-94-2152 ファクス番号:0248-94-4563
特撮文化推進係 電話番号:0248-94-7174 ファクス番号:0248-94-4563
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。