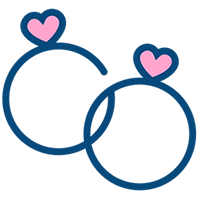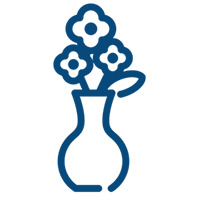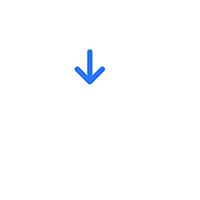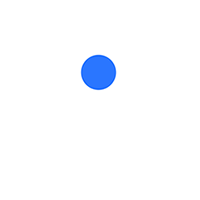高額医療・高額介護合算療養費制度(国民健康保険)
高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療保険と介護保険の両方の自己負担額が高額になり、1年間(毎年8月~翌年7月末)にお支払いされた自己負担額の合計が、基準額(下記表の自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
医療保険と介護保険で、それぞれの1ヶ月の限度額(高額療養費と高額介護サービス費)を適用した後、年間の自己負担金額を合算し算出します。
同じ世帯で医療保険と介護保険の両方の自己負担額がある世帯が対象となり、70歳未満の方の医療保険の自己負担額は、1ヶ月21,000円以上のみを合算の対象とします。
高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
70歳未満の基準額(自己負担限度額)
| 所得区分 所得要件 |
自己負担限度額 平成26年7月以前 |
自己負担限度額 平成26年8月から 平成27年7月 |
自己負担限度額 |
|---|---|---|---|
| 上位所得者 基礎控除後の所得 901万円超 |
126万円 | 176万円 | 212万円 |
| 上位所得者 基礎控除後の所得 600~901万円以下 |
126万円 | 135万円 | 141万円 |
| 一般所得者 基礎控除後の所得 210~600万円以下 |
67万円 | 67万円 | 67万円 |
| 一般所得者 基礎控除後の所得 210万円以下 |
67万円 | 63万円 | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 | 34万円 | 34万円 |
- ※基礎控除後の所得とは、国保被保険者の総所得金額などから基礎控除額(33万円。令和3年8月診療分からは43万円。ただし、合計所得金額2,400万円超の高所得者の場合は、基礎控除額が少なくなります。)を引いた後の所得の合計額。所得申告がなく所得判定のできない場合も上位所得者とみなします。
- ※住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯。
70~74歳の基準額(自己負担限度額)
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得世帯3 | 212万円 |
| 現役並み所得世帯2 | 141万円 |
| 現役並み所得世帯1 | 67万円 |
| 一般世帯 | 56万円 |
| 低所得II世帯 | 31万円 |
| 低所得I世帯 | 19万円 |
- ※現役並み所得者とは同じ世帯に一定以上の所得(住民税課税所得が145万円以上)ある70歳以上の国保被保険者がいる方と、平成27年1月以降に70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の「総所得金額」の合計額が210万円を超える世帯の方。ただし70歳以上の国保被保険者(国保被保険者であった後期高齢者医療制度被保険者も含む)の収入額の合計額が一定の収入未満(単身世帯:年収383万円未満、複数世帯:年収520万円未満)の場合は申請により「一般所得者」となります。
- ※75歳以上等で後期高齢者医療制度に加入している方の自己負担限度額は、別に定められておりますので、後期高齢者医療制度保険者へ確認してください。
- ※低所得I世帯とは、合計所得額が「0円」の世帯。年金収入がある方はその収入額が「80万円以下」の世帯。なお、令和3年8月診療分から、住民税非課税世帯の給与所得者は、給与所得の金額から10万円を控除します。
- ※低所得I世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は低所得I世帯で算出しますが、介護保険からの支給は低所得II世帯で算出されます。
高額医療・高額介護合算療養費制度の対象とならないもの
- 入院時の食事代や差額ベッド代等の保険診療以外のもの
- 施設サービス等での食費・居住費(滞在費)、その他日常生活費
- 福祉用具購入費、または住宅改修費の1割負担分
- 要介護状態区分別の支給限度額を超えてサービスを利用したときの利用者負担
支給額の計算方法
自己負担を合算した世帯の負担額から、基準額(自己負担限度額)を差し引いた分が支給されることになり、その金額は、医療保険と介護保険であん分し、それぞれから支給および通知されます。
ただし、支給額が「500円以下」の場合は支給されません。
70歳未満の所得区分が一般、2人世帯で平成25年8月から平成26年7月までの負担額が、被保険者Aに医療保険420,000円、被保険者Bに介護保険280,000円の負担がある場合
- 自己負担額合計の計算
420,000円+280,000円=700,000円 - 支給金額の計算
700,000円-670,000円=30,000円 - 支給金額のあん分
(医療保険分)←医療保険者から支給
30,000円×(420,000円÷700,000円)=18,000円
(介護保険分)←介護保険者から支給
30,000円×(280,000円÷700,000円)=12,000円
申請方法
- 基準日である7月末日現在に加入する医療保険者へ申請します。
- 8月から翌年7月末日の間に加入する医療保険や介護保険等が異なる場合、各医療保険者や介護保険者等から「自己負担額証明書」を交付していただき、それを添付することとなります。
申請に必要なもの
- 世帯主及び該当者の個人番号が確認できる書類
- 窓口に来る人の本人確認ができる書類
- 世帯主の預金通帳
申請場所
保険年金課国保給付係
支給方法
現金支給又は指定の口座に振り込みます。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。